私立学校では土曜授業の有無とか、定期試験後の長めの休みとか、その学校の考え方で授業日が組まれています。この点、基本的に週5日授業で無駄な休みが無く運営される公立学校とは大きな違いがあります。
チリ太郎の学校では毎週土曜日に半日授業があるので、生徒は大変だなと思います。その一方で、思わぬ平日に学校休業日がある月があり、「これは何のための休み?」みたいな不思議さを感じることがあります。
チリ太郎が中学生の頃は、この学校休業日をうまく使って家族でお出かけなどのイベントを組むことがありました。
チリ太郎が高校生となり、もう頻繁に家族で出かけるという雰囲気ではないものの、可能な限り家族全員で行動するようなイベントは続けるよう心掛けています。
つい先日、10月の終わりにも平日の学校休業日がありました。
私は頭の中で小旅行のプランなどを考えていたのですが、妻は横浜のそごう美術館で開催されている「ミッフィー展」に行くと言います。
さすがにチリ太郎にミッフィー展につき合わせるのは…、と思ったのですが、私のいつもの作戦である、
何かとセットにしたらいい感じのプランになるのでは?
という発想のもと、こんな場所とくっつけてチリ太郎に提案しました。

謎解きカフェ
果たして、チリ太郎にプランを提示したところ、割とあっさりとOKを貰えました。
○ミッフィー展

その昔、東京のどこかで開催されたミッフィー展にまだ赤ん坊であったチリ太郎を連れていった覚えがあります。(もちろん、行きたいと言ったのは妻です)
そんなわけで、チリ太郎は当然覚えておりませんが、家族としては2度目のミッフィー展。誕生70周年記念だそうな。
展示はディック・ブルーナさんの紹介に始まり、全てではありませんが、ブルーナさんが手がけたミッフィーシリーズの絵本の原画、デッサン、印刷稿などの展示が続きます。
しっかり見たので2時間以上かかりました。
以前に行ったミッフィー展はデパートの催事場みたいなスペースでしたが、それに比べると今回の展示はかなりボリュームがあった気がします。
チリ太郎ってこういう展示物があると、あまり読み飛ばしたりしないで文字をしっかりと追うように見て回るんですよね。
興味を持てないかなと心配しましたが、チリ太郎なりの視点で感想を述べながら見て回っていました。

チ:「1955年の誕生のときは今とかなり違うけど、1963年以降は今とほとんど変わらないデザインだね」
妻:「よく見てみると、耳の形とかが変わってるよ」
チ:「あっ、ほんとだ」
ミッフィーは非常にシンプルなデザインなのですが、絵本の作り方は結構特殊です。
凡そ以下のような感じです。
絵の図案を書く→透明なフィルムに線を焼き付ける→ブルーナ・カラーと言われる決まった色の色紙を切り抜き、フィルムに当てる→キャラクターの位置や色をいろいろ変えながら印刷稿を完成させる
ブルーナさんの経歴も興味深かったですが、上記のような手法にたどり着いた理由などを想像するのが楽しかったですね。見学者にそういうことを想像させる展示になっていたと思います。
ずっと立ちっぱなしでしたので、終盤はチリ太郎も少し疲れた様子を見せていましたが(私も疲れた)、想像以上にしっかりと付き合ってくれました。
なにしろ、買いもしないグッズ売り場まで見学してまわっていましたからね。妻も喜んだに違いありません
○謎解きカフェ
今回は横浜の謎解きカフェにお邪魔しましたが、系列のお店が新宿や銀座にあるらしいです。
こういうお店の場合、カフェとしてのクオリティはさほど重要ではありません。
問題は「謎解きが面白いかどうか」だと思うのですが、そういうのは実際に行ってみないとわかりません。
謎解き代1,600円とワンドリンクを注文し、滞在時間に制限はありません。
比較的難易度が高めで標準時間30分~の謎解きを選んでみました。
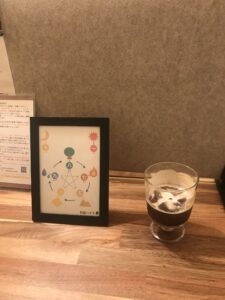
ネタバレ禁止なので撮影OKのものだけ。 この他にも鍵付きの箱とか小道具がありました。
昨年、東京ドームシティの謎解きイベントに参加した記事を書きました。
チリ太郎は単純なクイズよりも謎解き系の問題の方が好きなようで、こういうお店を提案できたのは我ながらヒットでした。(興味を引くことができたと思います)
肝心の謎解きですが…
難しかった!
というか、それで丁度良かった。
チリ太郎はノーヒントで適度に悩みながら解き切りました。
遅れて私がヒントをもらいながら終了。
妻もヒントをもらいながら、なんだかんだ2時間ぐらいかかりましたかね。
※ヒントはLineに指定の入力をすることでもらえます
終わった後も、将棋の感想戦のように、
「ここの問は全然ひらめかなくて最後まで残った」
とか、
「一番最後の重要なカギに気づいたのはおとさんだ」
「そういうおとさんは、2巡目の問いで同じ間違いをしていた」
とか、
「ただ紙に書いてある問題を解くだけでなくて、小道具などもあって楽しいよね」
など、なかなか話が弾みました。
こういうの、誰かがついてこられないとか、心が折れてしまうようなレベルだと、なんだか楽しく終われないものです。
そういう意味では、大人が苦戦しつつもなんとか終了できたという点で、我々にとっては難易度の選択が丁度良かったと思います。